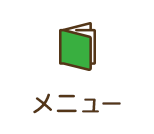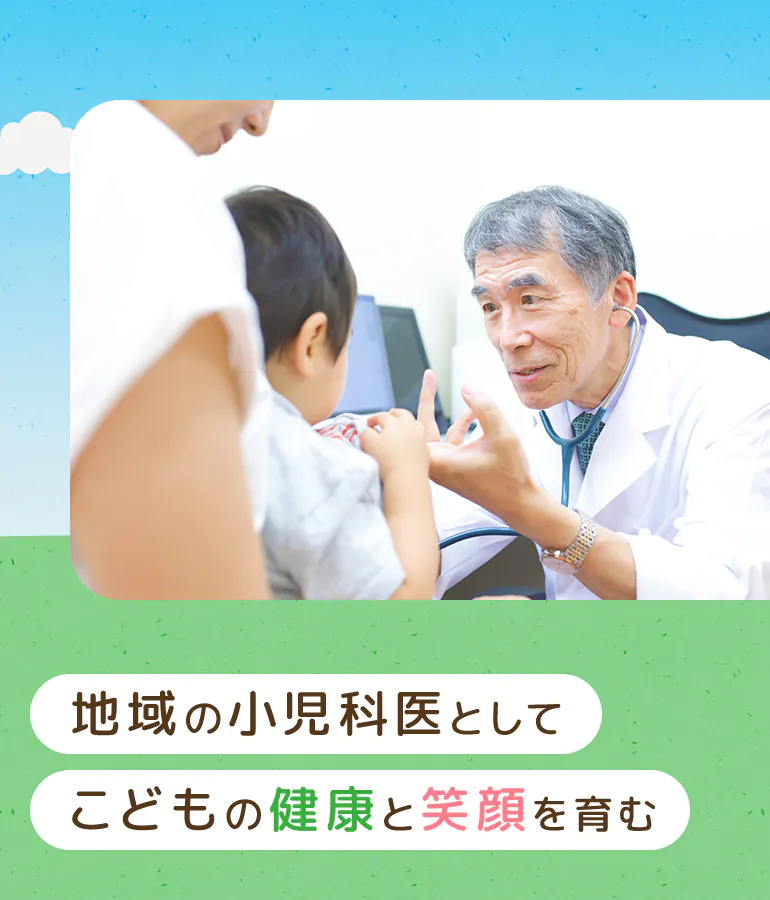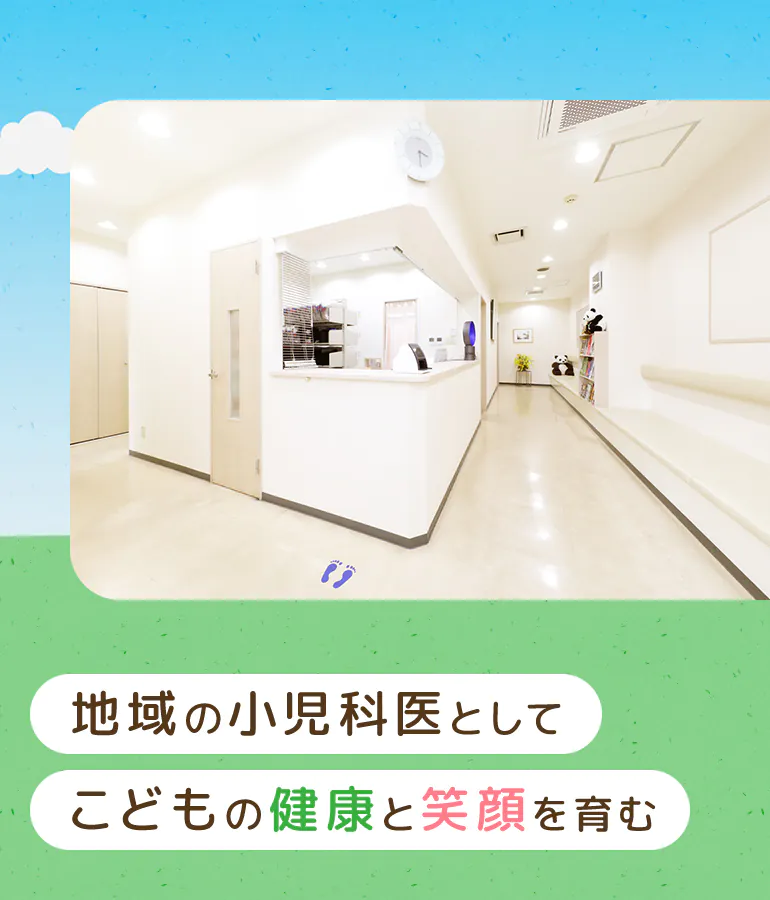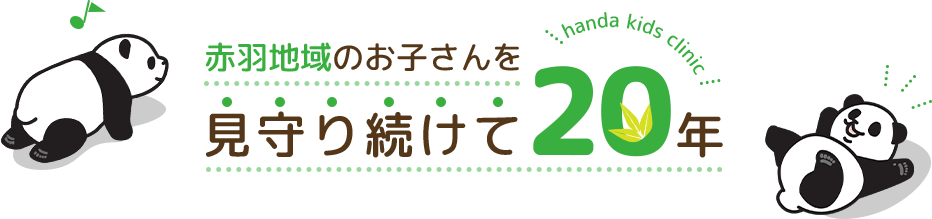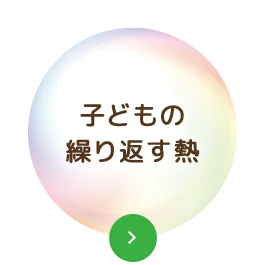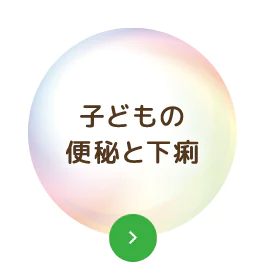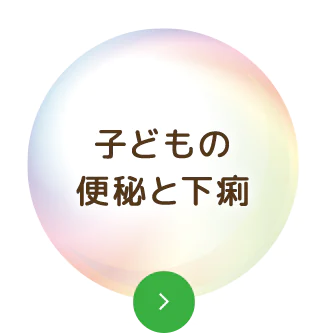お知らせnews
- 2024年4月15日
- 時間変更のお知らせ
- 2024年4月3日
- MRワクチンについて
- 2024年3月16日
- 診療時間のお知らせ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-12:00 【非感染枠】 9:30-11:00 |
● | ● | ● | ● | ● | ◎ | - |
| 14:00-18:00 【非感染枠】 14:00-16:00 |
● | ● | - | ● | ● | - | - |
【休診日】水曜午後、土曜午後、日曜、祝日
◎…8:30-13:00
※9:30-11:00は非感染枠
※14:00-16:00は、乳幼児健診と予防接種を含む非感染枠です。
(乳幼児健診は予約制のため優先です。)
※非感染枠:風邪症状以外の方
〒115-0045
東京都北区赤羽2-69-4
クリニックプラザ21-2F
TEL 03-3901-7433 / FAX 03-3901-7438
※言葉で説明が難しい場合はFAXをご活用ください。